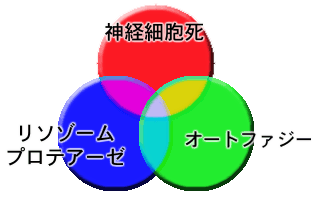
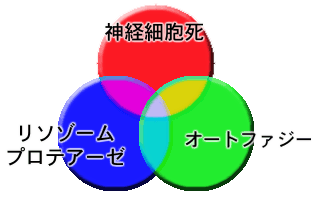
リソソームプロテアーゼ、オートファジーそして神経細胞死神経細胞のモデル細胞株として広く用いられているPC12細胞は、血清を除いた培地で培養するとアポトーシスに陥る。この時、アポトーシスの実行因子として知られるカスパーゼとカスパーゼ依存性DNaseが順次活性化され、細胞は死に至る。形態学的にアポトーシスの過程を調べてみると、核の変化に先行して細胞質にたくさんのオートファゴソームが出現する事が分かった。オートファジー(自食作用)は細胞内代謝回転或いは細胞がおかれている環境の変化(飢餓状態など)に伴い細胞自身の構成要素をリソソーム系で分解する現象で、細胞の恒常性や生存を維持するために働いていると考えられる。私達はこのオートファジーを抑制するとPC12細胞のアポトーシスも抑制されることを見い出した。世界的に見ると、この”オートファジー死”に関連する研究報告も増えつつある。近年、オートファジーに関わる分子機構に関する研究は酵母で飛躍的に発展している。高等動物においても類似の機構が存在する事が予想されることから、私達もこの面からオートファジー死の解析を始めている。アポトーシスの過程でオートファジーが促進される事から、私達はさらにリソソームプロテアーゼの細胞死への関与について解析を行った。その結果、アポトーシスの進行に伴い、アスパラギン酸プロテアーゼであるカテプシンDの活性と蛋白量が増加し、システインプロテアーゼであるカテプシンBは逆に激減することが分かった。これらのプロテアーゼをコードする遺伝子をPC12細胞に導入するとカテプシンDは細胞死を促進し、カテプシンBは細胞の生存活性を上昇させる事が明らかとなった。このことはリソソームの酵素を介した細胞死の経路が存在することを示唆している。この経路でカテプシンDの基質となり、細胞死誘導に関連する蛋白質の同定、さらにはオートファジーの誘導からこの経路に至る一連のカスケードにおける実行因子の解明を進めている。中枢神経の正常と異常で、これらリソソームカテプシン群が重要な役割を演じていることは、これら酵素を欠損する動物や細胞を解析する中で明らかになりつつある。特にカテプシンDは神経性セロイド-リポフスチン蓄積症の原因遺伝子の一つと考えられる所見も得ている。神経細胞死回避因子の探索神経細胞は、生存を維持するために細胞外からの多くの刺激を必要としている。その刺激が失われると、速やかに細胞死を誘導し、その多くがアポトーシスの特徴を示すことから神経細胞死にアポトーシスが深く関わっていると考えられている。我々は、PC12細胞の培養上清から、血清除去によるPC12細胞の細胞死を抑制する活性を持った35kDaの液性因子を単離、同定し、PCTF35(PC12 derived Trophic Factor)と名付けた。PCTF35はヒト、マウス、ラットに広く保存された分泌性糖蛋白質で胎生初期に神経系組織での一過性の発現が見られることから、神経分化との関与が示唆されている。また、PCTF35はNGFと相乗的にPC12細胞の細胞死を回避させることが分かっており、現在その作用機序を解析している。 |
| 神経細胞死の制御機構 1)細胞死制御に関わるプロテアーゼの解析(井佐原、金森、柴田) リソソームカテプシン群により制御される細胞死 2)オートファジーと細胞死(大沢、亀高) 3)Bcl-2蛋白の機能解析(金森、富山、柴田) |
| 神経生存・分化(栄養)因子の探索(大沢、亀高、張) 1)PC12細胞由来の新規栄養因子の解析 発現・分布・生理機能・細胞内シグナル伝達の解析 2)PC12細胞由来の新規栄養因子と関連蛋白の探索 |
| リソソームの生理的役割 1)カテプシンBおよびD欠損マウスの解析(小池) (神経性セロイドリポフスチン症の解析) 2)新規プロテアーゼの探索(亀高、柴田) |
|
マンノース6-リン酸リセプターと細胞内輸送 (生細胞における細胞内輸送経路のVisualization) |